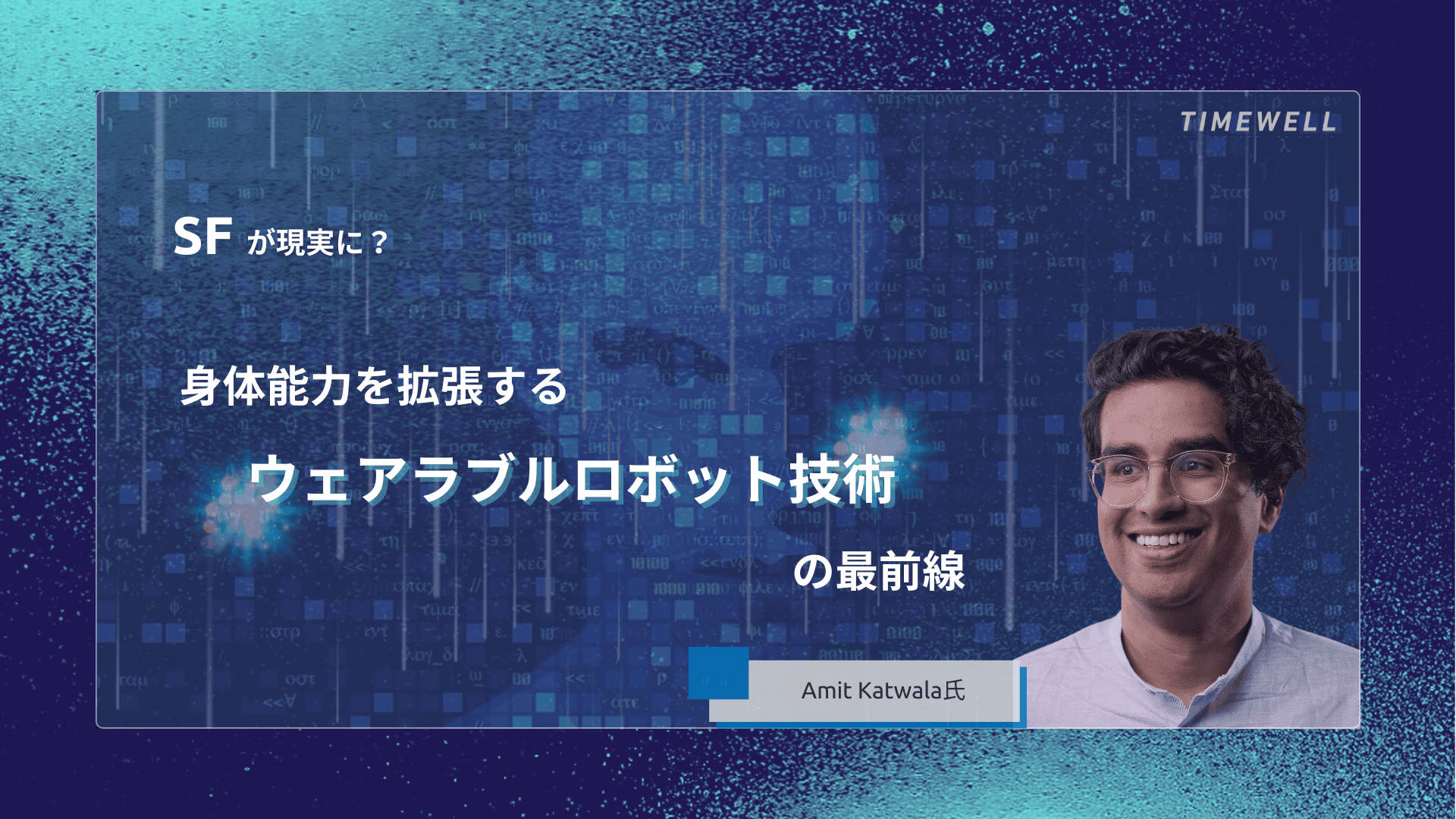株式会社TIMEWELLの濱本です。
「もう一本、手があったら」「親指がもう一つあれば」。日常生活や仕事の中で、ふとそんな願望を抱いたことはないでしょうか。SF映画やアニメの世界で描かれてきた、人間の身体能力を拡張するテクノロジー。それが今、現実のものとなりつつあります。
WIREDのライター兼編集者であるAmit Katwala氏は、まさにその最前線を体験すべく、日本の研究室へと足を運びました。彼が目の当たりにしたのは、装着することで人間の可能性を飛躍的に高める可能性を秘めた、驚くべきウェアラブルロボットたちでした。これらのロボットは果たしてどれほど使いやすく、動きは自然なのか?物を掴むことはできるのか?そして何より、これらを装着することで人間は「超人」になれるのでしょうか?
本記事では、Amit氏の体験を通して、東京大学で開発されたウェアラブルロボットアームと、ケンブリッジ大学で研究が進む「第三の指」という、二つの革新的な人間拡張技術を深掘りします。これらの技術が私たちの働き方や生活、さらには人間という存在そのものにどのような変革をもたらすのか、その可能性とビジネスへの応用を探ります。
東京大学発・装着型ロボットアーム:伝統と革新技術が融合した人間能力拡張への挑戦 ケンブリッジ大学発・「第三の指」が切り拓く新たな身体感覚と操作性 脳は新たな身体をどう受け入れるか?人間拡張の神経科学的側面と未来展望 まとめ 東京大学発・装着型ロボットアーム:伝統と革新技術が融合した人間能力拡張への挑戦
Amit氏が最初に訪れたのは、東京大学の稲見昌彦教授らが研究開発を進める装着型ロボットアームの現場です。このロボットアームの設計思想には、日本の伝統的な人形浄瑠璃が影響を与えているといいます。人形浄瑠璃では、一体の人形を複数の人形遣いが操り、あたかも人形が自らの意志で動いているかのような複雑で滑らかな動きを生み出します。このロボットアームもまた、人間の能力を楽器のように拡張し、新たな可能性を引き出すことを目指して設計されました。
稲見教授によれば、このシステムは基本的に「動きの小さなコピー」を拡大してロボットアームに伝える物理コンピューティングの一例です。衝突回避の仕組みも組み込まれており、直感的に理解しやすい操作性を目指しています。
具体的には、操作者(パペットマスター)が装着する小型の装置に内蔵されたセンサーが関節の角度を測定し、そのデータはラップトップ内の3Dモデルに送られ、そこで処理された情報が大型のロボットアームを精密にコントロールするという仕組みです。システムは、バックパック、アームを接続するソケット、アーム本体のモーター、そして手首のモーターから構成され、各関節はカーボンの骨格で繋がれています。これは、まるで人体の骨のような役割を果たし、全体の構造を支えています。
Amit氏が実際にこのロボットアームを装着してみると、その重量感にまず気づきます。背負ったバックパックはそれなりに重く、体を動かすとロボットアームが追従して動く感覚があるものの、意外にも快適だったと述べています。外見はまるでロボットと融合したかのようで、「シルエットが最高にクールだ」と興奮を隠せません。
稲見教授がパペットマスターを操作してロボットアームを動かすデモンストレーションでは、Amit氏はアームが振動し、自分の意図とは無関係に手足が動くという奇妙な感覚を体験します。肩の部分が振動しながらアームを上下させる音や、モーターの作動音がはっきりと聞こえ、これだけの質量を持ち上げるためにどれほどの力が必要とされているかを実感したといいます。その音は機械的でありながら、どこか生物的、まるで動物が喉を鳴らしているようにも感じられたそうです。自分自身と握手するという体験は、彼にとって非常にユニークなものでした。
次に、人間が目を開けずに自分の手足の位置を把握できる能力「プロプライオセプション(自己受容性感覚)」を、このロボットアームでも感じられるかのテストが行われました。目を閉じた状態で稲見教授がロボットアームを動かし、Amit氏がどの腕がどのように動いているかを当てるというものです。最初は左上のアームが上下に、次に右下のアームが動き、さらに左右両方のアームが動いていることを、Amit氏は体感として捉えることができました。体の傾きや肩への振動から、特定のアームの動きを推測できたのです。例えば、体が右に傾き、右肩に振動を感じたことから、右下のアームが動いていると判断しました。両方のアームが動いた際には、約4キロの追加重量によって体がバランスを崩し、無意識にカウンターバランスを取ろうとしている自分に気づきました。
続いて、Amit氏は自身でコントローラーを操作してみました。ロボットアーム本体の重厚感とは対照的に、コントローラーは非常に軽量で、そのギャップに驚いたようです。そのため、最初は非常に操作が慎重になり、他人に操作してもらう方がむしろ安心感があったと述べています。自分で操作する場合、自分の手の急な動きで、意図せずロボットハンドで顔を叩いてしまう可能性を考え、自然と動きが慎重になったのです。
最後に、ロボットアームが実際に物を掴む能力をテストしました。Amit氏の役割は、ロボットと「協力」して物を掴むことです。最初の挑戦は、柔らかい小鳥のぬいぐるみ。これは見事に成功しました。次に、ボールを掴むテストでは、両手(ロボットアーム)が必要となり、何度か試行錯誤を繰り返しながらも、最終的には成功を収めました。最も難易度が高かったのは、ペンを掴んでロボットに渡し、蓋を取り、ロボットに何かを書かせるという一連の作業でした。ペンを正確に掴むこと自体が難しく、何度も失敗を繰り返します。最終的には文字を書くところまでは至らず、「アーティストの皆さん、ロボットに仕事を奪われる心配はまだなさそうだ」と冗談めかして締めくくりました。しかし、全体としては非常に感銘を受け、練習を重ねればさらに上手に扱えるようになるだろうと結論づけています。
稲見教授は、このロボットアームの将来的な応用可能性について、以下のような展望を語っています。
・超人スポーツ: この種のロボットアームを装着してプレイする新しいタイプのスポーツの創出。
・医療支援: 例えば、手術中に医師の手の代わりに器具を保持するなど、医療手術の補助。
・リハビリテーション: 遠隔地やコンピューターからの指示で腕の動かし方を教えたり、リハビリを支援したりする。
・スキル習得: 武道やその他の新しいスキルの習得を補助する。
全体として、Amit氏はロボットアームの性能に深く感銘を受け、練習を重ねればさらに使いこなせるようになるだろうと結論付けています。この東京大学での体験は、人間拡張技術の持つ大きな可能性を彼に実感させるものでした。
ケンブリッジ大学発・「第三の指」が切り拓く新たな身体感覚と操作性
東京での刺激的な体験を終えたAmit氏は、次なる人間拡張技術を求めて、より身近なイギリス・ケンブリッジへと向かいました。彼がそこで出会ったのは、Dani Clode氏と、彼女が所属するケンブリッジ大学プラスティシティ・ラボのチームが開発を進める「サード・サム(Third Thumb)」、つまり「第三の指」です。文字通り、手に装着するもう一本の親指というこの斬新なデバイスは、私たちの身体認識や運動能力にどのような変化をもたらすのでしょうか。
Dani Clode氏は、拡張・義肢デザインを専門とする研究者です。彼女が開発した「第三の指」は、驚くほどシンプルかつ洗練された構造を持っています。まず、手にはめ込む本体部分があり、ここから柔軟な素材で3Dプリントされた指が伸びています。この指は、手首に装着された2つのモーターによってワイヤーで牽引され、巧みに動きます。モーターの配置は腕時計とほぼ同じ位置で、非常にコンパクトです。これらのモーターや制御基板(PCB)は、足首周りや靴の中に装着された圧力センサーとワイヤレスで接続されており、バッテリーも交換可能な設計となっています。つまり、足の指の動きで「第三の指」をコントロールするという、直感的でありながらも新しい操作方法を採用しているのです。Amit氏が操作する際にモーターから聞こえる音は、彼に「小さなロボットか、スターウォーズのドロイドみたいだ」という印象を与えました。
Amit氏も早速この「第三の指」を装着し、操作を体験しました。両足の親指の下に圧力センサーが配置され、それぞれの足指を踏み込むことで「第三の指」の異なる動きを制御します。左足の親指を踏み込むと指が曲がり、右足の親指を踏み込むとまた別の動きをする、といった具合です。その動きは非常に滑らかで、Amit氏は「これはすごいクールだ!」と感嘆の声をあげました。特筆すべきは、その比例制御です。足の指で踏み込む力の強さに応じて、「第三の指」の動きの速さや強さが変わるため、非常に繊細な操作から素早く力強い動きまで、幅広いコントロールが可能になります。Amit氏も「ゆっくり優しく押すと、繊細なコントロールができる。速く押せば、素早く動く。かなりパワフルだね」と、その反応の良さと力強さに驚いていました。実際に、手のひらを「第三の指」で掴むと、かなりの圧力がかかるのが見て取れました。
操作方法を理解したAmit氏は、次に第3の指の能力を試す様々なテストに挑みます。
研究チームによれば、通常、人々は最初の1分以内に機能的に使えるようになるものの、より細かい運動スキルを習得するには1週間程度の練習が必要だといいます。最初のテストは「フルグリップ」。目標は、他の指を使わずに「第三の指」だけで物を掴むことです。これは基本的な練習として行われました。
次に、「ボール複数個持ち」。これは、自分の手で掴めるだけのボールを持ち、さらに「第三の指」を使って追加のボールを掴むというもので、手の機能を拡張する能力を試すテストです。Amit氏は4つのボールに挑戦しましたが、これは少し難易度が高かったようです。
そして「ペグテスト」。これは、第3の指を使いながら、手全体を正しい位置に持っていくという、普段無意識に行っている動作の協調性を試すものです。Amit氏は、「手全体を正しい位置に持っていくのがいかに重要かを、普段はそんなこと考えもしない」と、その難しさを語っています。
最後に挑戦したのは「ジェンガテスト」。2つのジェンガブロックを、一つは通常の指2本で、もう一つは指と「第三の指」で同時に掴み、積み上げるという高度な協調動作が求められるテストです。Amit氏は、このテストを「非常に難しい。10点満点で11点の難易度だ」と評価しました。特に、「第三の指」からの触覚フィードバックがないため、どれくらいの力で掴んでいるのかが分からず、東京で学んだ自己位置覚の重要性を再認識したようです。自分の親指との動きを同期させるのが非常にトリッキーだったと述べています。
これらのテストを通してAmit氏が感じたのは、この「第三の指」がまだ自分の身体の自然な一部とは感じられないということでした。「トングか何かで物を持っているような感覚」と表現しており、意識的で慎重な操作が必要であることを強調しています。また、手が自分から離れた位置にある場合、特に「第三の指」の位置を正確に把握することが難しく、対象物に対して手を正しく向けること自体が一つの挑戦だったようです。この経験は、新たな身体部位を効果的に活用するためには、視覚情報だけでなく、身体感覚や自己位置覚がいかに重要であるかを示唆しています。
脳は新たな身体をどう受け入れるか?人間拡張の神経科学的側面と未来展望
ウェアラブルロボットアームや「第三の指」といった人間拡張技術は、私たちの身体能力を物理的に向上させるだけでなく、それを操作する脳にも影響を与える可能性があります。Amit氏はケンブリッジ大学で、認知神経科学の専門家であるTamar Makin教授にも話を聞き、「第三の指」の使用が脳活動にどのような変化をもたらすのか、実際の実験に参加しました。
実験は、Amit氏がfMRI(機能的磁気共鳴画像法)スキャナーの中で、「第三の指」を操作したり、自分の手足の指を動かしたりするというものでした。Tamar Makin教授のチームは、この「第三の指」のようなデバイスを使い、参加者がこれまで経験したことのない全く新しい方法で身体を操作することで、手が持つ能力以上のことを達成できるようになるのかを研究しています。
スキャン結果は非常に興味深いものでした。Amit氏が自分の指を動かしているときには、脳の「手の領域」が活発に反応しているのが確認されました。これは予想通りの結果です。しかし、彼が「第三の指」を操作しているとき(つまり足の指を動かしているとき)には、驚くべきことに「手の領域」にはほとんど活動が見られませんでした。代わりに活発だったのは、「足の領域」だったのです。これは、「第三の指」をコントロールするために脳が手の筋肉ではなく、足の筋肉を使っていたことを明確に示しています。
Tamar Makin教授は、脳の運動皮質(動きをコントロールする領域)と体性感覚皮質(触覚や筋肉からの感覚情報を受け取る領域)の連携について説明しました。これらの領域は協調して働くことで、スムーズな運動制御を可能にしています。特に「手の領域」は、脳の中でも非常に重要な位置を占め、他の多くの脳領域と密接に連携しています。そして、「手の領域」は「足の領域」とも良好な接続性を持っているため、足の指で「第三の指」を操作するという直感的なデザインがうまく機能する理由の一つだと考えられます。Tamar Makin教授は、「デザインを賢く行い、直感的なデザインを考えれば、プラグアンドプレイで使える技術を作ることができる」と述べています。
「第三の指」を使う上で最も難しかったのは制御を学ぶことでしたが、将来的には、これらのロボット手足が脳に直接埋め込まれたチップを介して接続される可能性はあるのでしょうか?Tamar Makin教授は、現在はまだその分野の非常に初期段階にあるとしつつも、重要なのは「概念実証」であると強調します。人間は5本指の手に慣れ親しんでいますが、追加の指や腕を使う上での限界は、究極的には人間の想像力の限界であるというのです。彼女は、追加の身体部位を私たちの身体、脳、そして認知的な意識に組み込む方法は複数あり、これらの技術をより良く活用するために世界を再設計しない理由はないと力強く語りました。
Amit氏は、今回の取材を通して、すぐにでも追加の腕や親指が必要だと感じたわけではないとしつつも、バックパックを背負うのと同じくらい簡単に「超人」になれる世界のアイデアには「三本の親指を立てて賛成だ(three thumbs up)」と、ユーモラスに締めくくっています。この体験は、人間拡張技術が単なるSFの夢物語ではなく、現実的な未来として私たちの目の前に迫っていることを示しています。それは、リハビリテーションや障碍者支援、危険な作業の代替、あるいは全く新しい芸術表現やスポーツの創出など、計り知れない可能性を秘めています。ビジネスの観点からも、これらの技術は新しい市場やサービスを生み出し、既存の産業構造を大きく変える起爆剤となるかもしれません。
まとめ
東京大学のウェアラブルロボットアームとケンブリッジ大学の「第三の指」。Amit Katwala氏が体験したこれらの人間拡張技術は、私たちの身体観や能力の限界を大きく揺るがす可能性を秘めています。伝統的な人形浄瑠璃に着想を得た多機能アームは、人間の動作を補助し、新たなスキル習得や医療、さらにはエンターテイメント分野での応用が期待されます。一方、足で操作する「第三の指」は、より日常的なレベルでの身体機能の拡張を目指し、脳が新たな身体部位をどのように認識し、制御するのかという神経科学的な問いにも光を当てています。
これらの技術はまだ開発の途上にあり、操作性の向上や触覚フィードバックの実装など、解決すべき課題も少なくありません。しかし、稲見教授やTamar Makin教授が指摘するように、これらの技術の限界は、技術そのものよりもむしろ私たちの想像力にあるのかもしれません。脳は驚くほど柔軟であり、適切に設計されたインターフェースを通じて、新たな身体パーツを自己の延長として認識し、活用する能力を持っています。将来的には、より直感的な制御システムや、さらには脳直結インターフェース(BMI)のような技術が登場し、SFの世界で描かれてきたような身体拡張が現実のものとなる可能性も否定できません。
もちろん、人間拡張技術の進展は、倫理的、社会的な課題も伴います。どこまでが人間で、どこからが機械なのか。技術へのアクセスにおける格差は許容されるのか。これらの問いに対する答えを社会全体で模索していく必要があるでしょう。Amit氏の体験は、テクノロジーが私たちの身体能力だけでなく、自己認識や社会のあり方にも影響を与える未来を予感させます。バックパックを背負うように身体機能を拡張できる世界は、もはや遠い夢物語ではないのかもしれません。その時、私たちはどのような「人間」になっているのでしょうか。その答えは、これからの技術開発と、私たち自身の選択にかかっています。