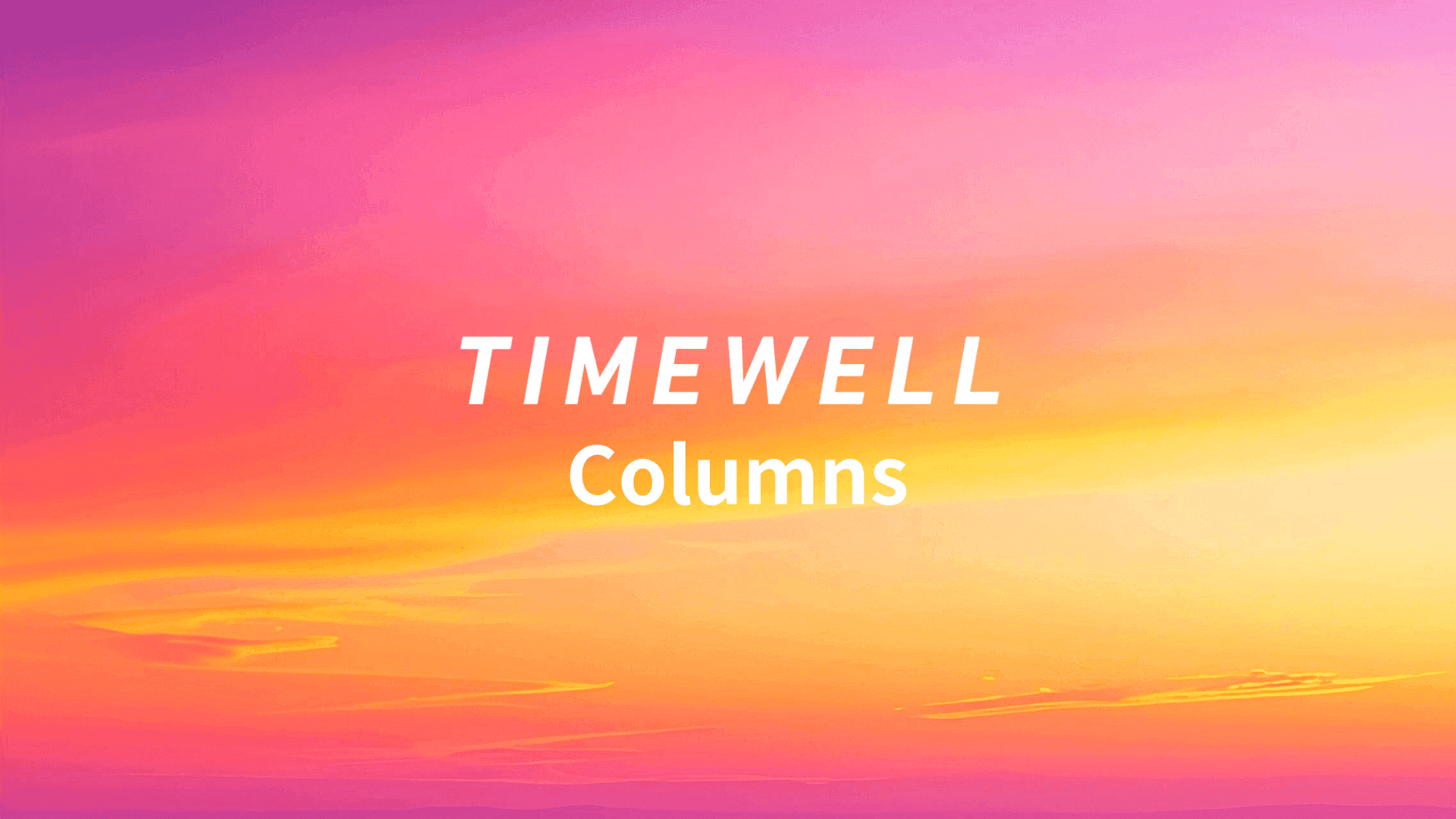こんにちは、TIMEWELLの濱本です。今日はテック関連のサービスご紹介です。
…と言いたいところなんですが、今回は少し趣向を変えます。テーマは投資契約。聞いただけで眠くなりそうな響きかもしれません。でも、この話、日本の未来を左右するくらいデカい話なんです。
きっかけは、弁護士の宮下和昌さんがYouTubeで公開された「グローバル型スタートアップのための投資契約の設計視点」という動画でした。宮下さんはIGPI弁護士法人の代表弁護士で、日本取締役協会の会長補佐も務めている方です。経済産業省が2025年9月に発表した「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項 増補版」を、実務家の視点から噛み砕いて解説されている内容なのですが、これがもう、めちゃくちゃ面白い。
契約書の話が面白いって、どういうことか。
この動画が突きつけているのは、日本のスタートアップが世界で勝てない理由が、技術力でも人材でもなく、投資のルールにあるという事実です。しかもそのルールは、世界から見るとガラパゴスと呼ばれるほど特殊なもの。経産省の新ルールは、この鎖国状態を終わらせるための、かなり本気の一手です。
この記事では、新ルールの中身と、なぜ今こんな話が出てきたのかという社会的背景を、スタートアップや投資に詳しくない方にも伝わるように、私なりに噛み砕いて書いてみます。
日本のベンチャー投資、その知られざる「ねじれ」の歴史
今回の経産省のルール変更がなぜ「起死回生の一手」とまで言えるのか。その意味を深く理解するためには、少し時間を遡って、日本のベンチャーキャピタル(VC)が歩んできた、特異な歴史を知る必要があります。
第一次から第三次までの「見せかけのブーム」
日本に初めて民間のVCが誕生したのは1972年のこと。京都エンタープライズディベロップメントを皮切りに、翌年にかけて8社のVCが相次いで設立されました。これが日本の「第一次ベンチャーブーム」です。現存する最古にして最大のVCであるジャフコ(当時は日本合同ファイナンス)も、この時に産声を上げています。[10]
しかし、その実態は苦難の連続でした。当時はまだ、現在のように投資家から資金を集めてファンドを組成する仕組みが未整備。VCはわずかな自己資本と親会社からの借入金を元手に、未公開企業に投資するしかありませんでした。投資先が成長して株式を公開し、利益が生まれるまでには何年もかかる。多くのVCが立ち行かなくなりました。
転機が訪れたのは1982年。アメリカの「リミテッド・パートナーシップ」を参考に、日本で初めて「投資事業組合」が組成されます。これは、複数の投資家から資金を集めてファンドを作り、そこからスタートアップに投資する仕組み。新たな資金調達の道が開けたことで、1983年から86年にかけて60社以上のVCが設立され、「第二次ベンチャーブーム」が到来します。
さらに90年代後半、ITバブルの波に乗って株式公開が相次ぎ、「第三次ベンチャーブーム」が起こります。しかし、経団連のレポートは、これらのブームの実態について、衝撃的な事実を指摘しています。
この 30 年間、3 度のベンチャー・ブームがあったわけですが,この主役はベンチャー・キャピタルであり株式公開会社であって,創業ブームが起こったということではありません。本来ベンチャー・ブームというのは,ベンチャー企業そのものの創業が活発に行われるということであるべきなんでしょうが,実際にはこの間,いわゆる開業率というのは低下する一方でありまして... [10]
つまり、VCや株式市場が盛り上がっているように見えても、社会全体で新しい会社を興そうという「起業」の動きは、むしろどんどん下火になっていた。これが、日本のベンチャー・エコシステムが抱える、根深く構造的な「ねじれ」の正体でした。
なぜ「育てる投資」ができなかったのか
なぜ、日本では本当の意味での創業ブームが起きず、VCは「育てる投資」ではなく、もっぱら上場直前の企業に投資するだけの存在になってしまったのでしょうか。理由は大きく分けて2つあります。
一つは、VCの成り立ちです。日本のVCの多くは、銀行や証券会社の子会社として設立されました。親会社から出向してきた社員が数年で入れ替わる「ローテーション人事」が当たり前。長期的な視点で投資先の成長にコミットし、経営に深く関与するような専門人材が育ちにくい構造でした。
もう一つは、出口戦略の乏しさです。当時の日本では、スタートアップが投資を回収する手段は、株式公開(IPO)しかありませんでした。しかも、そのIPOの基準が非常に厳しく、設立から上場まで平均で30年もかかっていたのです。VCのファンドの運用期間は通常10年。30年もかかるなら、創業したての若い会社に投資しても、ファンドの期限内に回収できる見込みがない。結果として、VCは必然的に、上場が目前に迫った「レイターステージ」の、いわば「出来上がった」会社に短期間だけ投資して、上場したらすぐに株を売って利益を確定させる、というビジネスモデルに傾倒していきました。
ハイリスクでも大きなリターンを狙って、創業期の会社を支援し、育て上げる。それがベンチャーキャピタルの本来の役割であるはずが、日本のVCは「銀行の融資の延長線上」のような、低リスク・低リターンの投資に終始してしまったのです。
この「ねじれ」の構造こそが、日本のスタートアップが大きく育たない根本的な原因でした。そして、この構造に、経産省の増補版は真正面からメスを入れたのです。
お手本はイスラエル「Yozma(ヨズマ)」プログラム
実は、政府が主導して海外のVCを呼び込み、国内のベンチャーエコシステムを劇的に変革させた成功事例があります。それが、1993年にイスラエルで始まった「Yozma(ヨズマ)」プログラムです。[11]
当時のイスラエルも、日本と同様に国内のVC市場が未成熟で、リスクマネーの供給が乏しいという課題を抱えていました。そこでイスラエル政府は、1億ドルの政府系ファンドを設立。そのうち2000万ドルは政府が直接投資し、残りの8000万ドルを「呼び水」として使いました。
具体的には、海外の有力なVCがイスラエルでファンドを設立する場合、政府が40%を共同出資するというインセンティブを与えたのです。さらに、そのファンドが成功した場合、海外VCは政府の出資分を安い価格で買い取ることができる、という破格の条件も付けました。
結果として、アメリカやヨーロッパのトップVCが次々とイスラエルに進出。彼らが持ち込んだ資金と、シリコンバレー流の「ハンズオン」による経営支援のノウハウによって、イスラエルのスタートアップは質・量ともに飛躍的な成長を遂げました。Yozmaプログラムは、わずか5年で民営化され、今日の「スタートアップ大国イスラエル」の礎を築いたのです。
今回の経産省の取り組みは、まさにこのイスラエルの成功モデルを日本で再現しようという試みと見ることができます。
なぜ今、国はこれほどまでに「スタートアップ」に賭けるのか
「失われた30年」という長いトンネル
そもそも、なぜ今、国を挙げてこれほどまでにスタートアップ支援が叫ばれるようになったのでしょうか。その背景には、バブル経済の崩壊から始まった「失われた30年」と呼ばれる、日本経済の長い停滞があります。
1989年末、日経平均株価は史上最高の3万8915円を記録しました。しかし、その直後から株価は暴落。土地の価格も下落し、多くの企業や銀行が巨額の不良債権を抱え込みました。これがバブルの崩壊です。
問題は、その後の対応でした。政府や日銀は、抜本的な構造改革ではなく、財政出動や金融緩和といった対症療法に終始します。痛みを伴う改革を先送りし、本来であれば市場から退出するはずの生産性の低い企業を、いわば「延命」させてしまったのです。[12]
結果として、日本経済の新陳代謝は滞り、産業の競争力は低下。企業は利益を上げても、将来への不安から賃上げや設備投資には回さず、内部留保として溜め込むばかり。個人消費も冷え込み、経済は縮小均衡に陥っていきました。
この30年間で、アメリカの株価が約9倍になったのに対し、日本の株価は未だにバブル期の最高値を超えることができていません。世界第2位を誇ったGDPも、2023年にはドイツに抜かれて4位に転落。スイスのビジネススクールIMDが発表する世界競争力ランキングでは、1989年から92年まで4年連続で1位だった日本は、2024年には過去最低の38位にまで沈みました。[16] かつての「経済大国」の面影は、もはやありません。
シンガポールの躍進に学ぶべきこと
対照的に、この30年で目覚ましい経済成長を遂げたのがシンガポールです。一人当たりGDPでは、1990年代には日本とほぼ同水準でしたが、現在では日本の2倍以上に達しています。
シンガポールの成功の要因は一つではありませんが、その根幹にあるのは、政府主導による徹底した「選択と集中」です。法人税を低く抑え、世界中から企業と人材を呼び込む一方、有望な成長分野を見定めては、手厚い助成金や支援プログラムを投入してきました。
特にスタートアップ支援にかける熱意は凄まじいものがあります。例えば、「Startup SG Founder」というプログラムでは、シンガポール国籍の起業家に対して、5万シンガポールドル(約580万円)の助成金と、専門家による手厚いメンタリングを提供しています。[13] さらに、外国籍の優秀な起業家や投資家には「EntrePass」という特別なビザを発給し、家族帯同での滞在を認めるなど、国策として世界中の才能を惹きつけているのです。
翻って日本はどうか。あらゆる産業を「広く薄く」守ろうとするあまり、結果としてどの分野でも世界に勝てない、という状況に陥ってはいないでしょうか。シンガポールの事例は、限られた資源の中で国が成長していくためには、痛みを伴う「選択」が不可欠であることを示唆しています。
次の「飯のタネ」を見つけなければならない
人口減少と高齢化が急速に進む中で、かつて日本経済を支えた製造業や自動車産業に代わる、新たな成長エンジン、次の「飯のタネ」を見つけなければ、この国は本当に沈んでしまう。この強烈な危機感が、政府をスタートアップ支援へと突き動かしているのです。
革新的な技術やビジネスモデルで、新たな市場を創造し、世界から富を獲得する。そんな力を持つスタートアップを一つでも多く生み出し、育てることが、日本経済再生のための最後の切り札だと考えられているのです。
そもそもスタートアップとは何か、なぜ国が本気で支援するのか
スタートアップとは、革新的なアイデアや技術をもとに、短期間で急成長を目指す企業のことです。街のラーメン屋さんが新しく開業するのとは少し違って、まだ世の中にない製品やサービスで市場を切り拓き、数年で何十倍、何百倍にも成長することを狙っている。Google、Amazon、Appleも、もとはガレージや大学の寮から始まったスタートアップでした。
なぜ国がこれほど本気で支援しようとしているのか。
答えはシンプルで、日本経済の次のエンジンが必要だからです。高度経済成長を支えた製造業は成熟し、人口は減り続けている。この先、日本が豊かであり続けるためには、新しい産業を生み出し、世界から稼げる企業を育てるしかない。その担い手として期待されているのがスタートアップです。
2022年11月、当時の岸田政権はスタートアップ育成5か年計画を策定しました。2027年度までにスタートアップへの投資額を10兆円規模に引き上げ、ユニコーン企業を100社創出するという、かなり野心的な目標を掲げたのです。ユニコーン企業とは、時価総額10億ドル(約1500億円)以上の未上場企業のこと。世界を変えるポテンシャルを持つ企業の代名詞です。[1]
計画策定から3年が経ち、スタートアップの数自体は2021年の約16,100社から2025年には約25,000社へと1.5倍に増えました。大学発スタートアップも2021年の3,305社から2024年には5,074社に伸び、しかもその増加分の約57%が東京以外の地域から生まれています。裾野は確実に広がっている。[2]
ただし、問題は高さです。ユニコーン企業の数は、2021年の6社から2025年時点で8社。目標の100社にはほど遠い。資金調達額も、2021年の8,857億円から2024年は8,748億円と、ほぼ横ばいのまま。10兆円の目標に対して、まだ1割にも届いていません。[2]
数は増えた。でも、世界で戦えるほど大きく育った企業がほとんどいない。これが日本のスタートアップ・エコシステムが今直面している最大の課題です。
日本のスタートアップが大きく育たない本当の理由
なぜ日本からはGAFAMのような巨大テック企業が生まれないのか。GAFAMとは、Google、Amazon、Facebook(現Meta)、Apple、Microsoftの5社を指す総称です。
この問いに対する答えは一つではありません。でも、突き詰めていくと、お金の流れ方と投資のルールという、2つの構造的な問題に行き着きます。
圧倒的に足りないリスクマネー
まず、お金の話から。国の経済規模に対して、どれだけベンチャー投資が行われているかを見てみます。
| 国・地域 | ベンチャー投資額のGDP比 |
|---|---|
| シンガポール | 2.61% |
| イスラエル | 2.10% |
| アメリカ | 0.64% |
| スウェーデン | 0.55% |
| イギリス | 0.47% |
| インド | 0.35% |
| 中国 | 0.23% |
| 韓国 | 0.22% |
| フランス | 0.19% |
| ドイツ | 0.18% |
| 日本 | 0.08% |
出典: 経済産業省 総合科学技術・イノベーション会議 資料 [3]
日本は0.08%。アメリカの8分の1。フランスやドイツの半分以下。シンガポールと比べると30分の1以下です。
宮下弁護士は、この数字について「国の稼ぐ力がベンチャー投資に十分あてがわれていない実態を物語るもの」であり、「国レベルでの両利きの経営が全く行えていない」と指摘しています。[4] 既存事業で稼ぎながら、同時に新しい事業にも投資する。企業経営では当たり前のこの考え方が、国全体としてはできていない。
結果として、ユニコーン企業の数にも如実に差が出ています。
| 国 | ユニコーン企業数 |
|---|---|
| アメリカ | 約690社 |
| イギリス | 55社 |
| フランス | 31社 |
| シンガポール | 15社 |
| 韓国 | 13社 |
| 日本 | 8社 |
出典: 経済産業省 スタートアップ・エコシステムの現状資料 [2]
日本のユニコーンとして名前が挙がるのは、Preferred Networks、SmartHR、Sakana AI、GOなど。どれも素晴らしい企業ですが、アメリカの690社という数字と比べると、桁が2つ違います。
上場ゴールという名の成長停止装置
お金が足りない中で、日本のスタートアップの多くが目指すのが早期のIPOです。IPOとはInitial Public Offeringの略で、自社の株式を証券取引所に上場し、一般の投資家が売買できるようにすること。本来は、さらなる成長に必要な大きな資金を市場から調達するためのスタートラインであるはずです。
ところが日本では、IPOがゴールになってしまっている。
日本のスタートアップがIPOで調達する金額は、中央値で見るとわずか数億円程度。これはシリーズAと呼ばれる創業初期の資金調達ラウンドで集める金額とほぼ同じ水準です。[4] 世界で戦うための大型投資をするには全く足りない金額で上場してしまう。上場ゴールという残念な言葉が生まれた背景には、こうした実態があります。
なぜこうなるのか。理由の一つが、日本のVCファンドの構造です。VCとはベンチャーキャピタルの略で、スタートアップに投資する専門のファンドのこと。
VCファンドには寿命があります。投資家からお金を預かって運用し、一定期間内にリターンを返す仕組みなので、だいたい10年程度で成果を出さなければなりません。ファンドの満期が近づくと、VCは投資先に対して早く上場してくれとプレッシャーをかけるようになる。スタートアップ側も、まだ十分に成長しきっていなくても、VCの都合に合わせて小さな規模で上場せざるを得なくなるわけです。
ベンチャーエンタープライズセンターの白書によると、日本では2019年から2023年の平均で、VCの投資回収手段の約70%が株式上場でした。[5] アメリカではM&Aが投資回収の大半を占めるのとは対照的です。M&Aとは企業の合併や買収のことで、大企業がスタートアップを丸ごと買い取る形の投資回収手段です。
グロース市場の構造的な歪み
小粒上場の受け皿になっているのが、東京証券取引所のグロース市場です。
グロース市場は、成長期待の高い新興企業向けの市場として設計されています。売上や利益がまだ小さくても上場できるという、世界でも珍しい仕組みを持っている。これ自体は悪いことではないのですが、問題は市場の投資家構成にあります。
グロース市場では、株式の売買と保有のいずれも5割以上を個人投資家が占めています。[6] プライム市場やスタンダード市場と比べて、長期的な視点で企業の成長を見守る機関投資家の存在感が薄い。
機関投資家が少ないとどうなるか。株価が短期的な話題性や個人の思惑で乱高下しやすくなります。企業としては、四半期ごとの数字に一喜一憂する市場の目を気にして、大胆な成長投資に踏み切りにくい。赤字を掘ってでも将来のために投資するという戦略が、日本のグロース市場では評価されにくいのです。
東証もこの問題を認識しており、2025年にグロース市場の上場維持基準を上場後5年で時価総額100億円以上に引き上げる方針を打ち出しました。[7] 小粒上場に事実上のNOを突きつけた形ですが、裏を返せば、それだけ問題が深刻だったということでもあります。
M&Aの足かせとなってきた「みなし清算条項」
そして、IPO偏重の構造をさらに強化してしまったのが、投資契約に含まれる「みなし清算条項」です。[14]
これは、会社が実際に解散・清算するわけではなくても、M&A(合併や買収)によって会社の支配権が他に移るような場合には、「会社を清算したものとみなして」、投資家が優先的に投資元本を回収できる、という契約条項です。
一見すると、投資家を保護するための合理的な条項に思えます。実際、まだM&Aが一般的でなかった時代には、創業者などが安値で会社を売り抜けてしまい、後から投資したVCが損をする、といった事態を防ぐために重要な役割を果たしました。
しかし、時代が変わり、M&Aがスタートアップの重要な出口戦略(イグジット)の一つとして定着してくると、この「みなし清算条項」が、むしろM&Aの足かせとなるケースが目立つようになります。
例えば、あるスタートアップが50億円で買収されるとします。VCが「1倍の参加型」という条件で10億円を投資していた場合、まずVCが10億円を優先的に回収します。残りの40億円を、創業者や他の株主で分けることになります。しかし、もし買収額が10億円だったらどうでしょう。VCが10億円をすべて持っていき、創業者や他の株主の手元には1円も残らない、という事態が起こり得たのです。
これでは、創業者はM&Aに応じるインセンティブが湧きません。むしろ、M&Aを避けて、無理にでもIPO(株式公開)を目指す、という歪んだ構造を生んでしまいました。結果として、日本では海外に比べてM&Aの件数も金額も伸び悩み、スタートアップエコシステム全体の成長を阻害する一因となっていたのです。
投資家を過剰に保護する「残余財産分配優先権」
そして、海外投資家が最も首を傾げるのが、日本の投資契約における「残余財産分配優先権」の扱いです。これは、会社が解散・清算する際に、残った財産を他の株主よりも優先的に受け取れる権利のこと。通常、VCがスタートアップに投資する際は、普通株式ではなく、この優先権が付いた「優先株式」を引き受けます。
この優先権自体は、リスクを取って投資するVCを保護するために、グローバルでも一般的に使われています。問題は、その中身です。
日本のVCが用いてきた優先株式には、「1倍の参加型」という条件が付いていることがほとんどでした。これはどういう意味かというと、
- まず、会社が清算する際に、VCは投資した金額(1倍)を最優先で回収する。
- それでもまだ財産が残っている場合、その残りの財産も、他の株主と同じ割合で分配を受ける(参加する)。
という二重に手厚い保護を受けられる、という意味です。例えば、VCが10億円を投資し、会社が50億円で清算されるとします。まずVCが10億円を回収し、残りの40億円を、VCと他の株主(創業者など)が持株比率に応じて分け合う。VCにとっては、元本割れのリスクを極限まで減らしつつ、アップサイドの利益も狙える、非常に有利な条件です。
この「残余財産分配優先権」が、実はクセモノでした。
海外投資家を門前払いするガラパゴス条項
国内にお金が足りないなら、海外から呼べばいい。当然そう思いますよね。
ところが、ここに最大の壁がありました。日本独自の投資契約の慣行、いわゆるガラパゴス条項です。
宮下弁護士はYouTube動画の中で、この問題を分かりやすく解説しています。海外のVCが日本のスタートアップへの投資を検討する際、技術や人材の実体審査に入る前に、投資契約の形式審査の段階で門前払いされてしまう、と。
具体的に何が問題なのか。大きく3つあります。
1つ目は、株式買取請求権。スタートアップが契約で定めた期間内にIPOできなかった場合などに、投資家が会社や創業者に対して投資した株を買い取れと請求できる権利のこと。アメリカにはこんな慣行は存在しません。[5]
スタートアップ投資は、10社に投資して1社が大当たりすればいい、というハイリスク・ハイリターンの世界です。失敗した時に起業家個人が株を買い戻さなければならないとなると、起業家は個人資産を失い、再起不能になりかねない。海外の投資家から見れば、失敗を許さない仕組みの中でイノベーションが生まれるわけがない、と映ります。
2つ目は、創業者への連帯保証。会社が契約に違反した場合に、創業者個人が会社と連帯して責任を負わされる条項です。会社と個人は別の法人格であるという近代法の大原則に反するもので、海外では考えられない。
3つ目は、IPO努力義務。投資契約の中に上場に向けて最大限努力することという条項が入っている。これがあるせいで、M&Aという選択肢が事実上封じられ、スタートアップは上場一択に追い込まれてしまう。
あるアメリカのVC幹部は、こう語っています。
グローバルスタンダードと異なる条項を含む投資契約は、我々にとってリスクが高すぎて投資できない [5]
契約書が日本語でしか作成されていないことも、英語圏の投資家にとっては大きな障壁です。世界で最も難しい言語の一つとされる日本語で書かれた契約書のリスクを正確に評価するためのコストが大きすぎて、検討する気にもならない。これが現実でした。
スタートアップ育成5か年計画と政策の転換点
ここまで読んで、日本のスタートアップ、かなりヤバいじゃん、と思った方も多いのではないでしょうか。政府もこの危機感を強く持っています。
岸田政権が打ち出した5か年計画
2022年11月、岸田政権はスタートアップ育成5か年計画を閣議決定しました。[1]
| 目標 | 数値 | 期限 |
|---|---|---|
| スタートアップへの投資額 | 10兆円規模 | 2027年度 |
| ユニコーン企業数 | 100社 | 将来目標 |
| スタートアップ創出数 | 10万社 | 将来目標 |
計画策定時のスタートアップ投資額は約8,200億円。これを5年で10倍以上にするという、かなり大胆な目標です。計画は人材、資金、事業の3本柱で構成されており、起業家教育の充実、エンジェル税制の拡充、海外展開支援など、多岐にわたる施策が盛り込まれました。
裾野の拡大から高さの創出へ
計画の前半3年間で、スタートアップの数は着実に増えました。しかし、先ほど見たように、ユニコーン企業の数は8社にとどまり、資金調達額も横ばい。裾野は広がったが、高さが出ていない。率直に言えば、そういう評価です。
経産省は2025年12月の資料で、5か年計画の後半戦のテーマを明確に示しています。それが高さの創出と継続。[2]
| 方向性 | 内容 |
|---|---|
| 成長資金の拡大 | M&Aやセカンダリーの促進。セカンダリーとは未上場株の二次取引のこと |
| グローバル・エコシステムのハブ化 | 海外投資家や人材を呼び込む環境整備 |
| ディープテックの成長 | AI、創薬、GXなど大規模投資が必要な分野の支援 |
| 地域エコシステムの形成 | 東京一極集中からの脱却 |
成長資金の拡大とグローバル・エコシステムのハブ化が最上位に来ている。海外から大きなお金を呼び込み、スタートアップを大きく育てることが、政策の最優先課題になったということです。
日米のフェーズ別資金供給の決定的な違い
なぜ成長資金がこれほど強調されるのか。日米のフェーズ別の資金供給を比較すると、理由が一目瞭然です。
| 投資フェーズ | 日本 | アメリカ |
|---|---|---|
| シード、つまり創業初期 | 17% | 9% |
| アーリー、つまり成長初期 | 70% | 33% |
| レイター、つまり成長後期 | 9% | 68% |
出典: 経済産業省 スタートアップ・エコシステムの現状資料 [2]
日本はシードとアーリーに投資が集中し、レイターはわずか9%。アメリカはレイターが68%を占めています。
日本のスタートアップは生まれるところまでは支援されるけれど、大きく育つための資金が圧倒的に不足している。赤ちゃんを産むところまでは手厚いけれど、大人になるまでの養育費が出ない。そんなイメージに近いかもしれません。
レイター期に必要な資金は数十億円から数百億円規模。日本のVCだけではこの規模の資金を供給するのが難しい。だからこそ、海外の巨大なVCファンドに入ってきてもらう必要がある。そのためには、海外投資家を門前払いしているガラパゴス条項を撤廃しなければならない。
こうした文脈の中で生まれたのが、経産省の増補版なのです。
経産省の新ルール「増補版」が投じた起死回生の一手
2025年9月、経済産業省は「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項 増補版」を策定しました。[8]
このガイドラインの歴史を簡単に振り返ると、初版は2018年に策定され、2022年に改訂。今回が3度目のアップデートとなる増補版です。
過去の版との最大の違いは、ガバナンスとグローバル対応という2つの視点が大幅に強化されたこと。単なる契約条項の解説にとどまらず、スタートアップの成長そのものを設計するための思想が盛り込まれています。
ポイント1: 株式買取請求権は設けるべきではないと明言
今回の増補版で最もインパクトが大きかったのが、この一言です。
過去のガイドラインでは、株式買取請求権について制限的に適用すべきという、やや曖昧な表現にとどまっていました。使うなとは言わないけど、控えめにね、くらいのニュアンスです。
増補版では、これが設けるべきではないに変わりました。[5] [8] 明確な否定。
この変更の意味は計り知れません。海外投資家が日本のスタートアップに投資する際、最初にチェックするのが既存の投資契約の内容です。そこに株式買取請求権が入っていた瞬間、この国の投資慣行はグローバルスタンダードと違うと判断され、検討対象から外されてしまう。
経産省が設けるべきではないと明言したことで、今後新たに締結される投資契約からこの条項が消えていけば、海外投資家にとっての参入障壁が大幅に下がります。
ポイント2: M&Aとセカンダリーを合理的な選択肢として明記
増補版では、スタートアップの投資の出口について、こう記載されています。
M&Aや株主間での未上場株式のセカンダリー取引も合理的な選択肢であり、発行体にとって望ましい場合もある [5]
これまで日本では、IPOが事実上唯一の出口でした。VCの投資回収の約70%がIPOによるものだったことは先述の通りです。
しかし、世界を見渡すと、スタートアップの出口としてはM&Aの方が圧倒的に多い。アメリカでは、スタートアップの大半がM&Aを通じて大企業の傘下に入り、そこでさらに大きく成長しています。
宮下弁護士が日本取締役協会の提言で指摘しているように、GAFAMの成長の原動力はスタートアップの買収でした。[4] Googleを例に取ると、検索エンジン以外の主要事業であるYouTube、Android、Google Maps、DeepMindなどは、すべて買収したスタートアップの事業です。Googleは自社の上にさまざまなスタートアップ事業を乗せていくプラットフォーマー的拡大を実現してきた。
その最たる成功事例が、2006年のYouTube買収です。当時、創業からわずか1年半、赤字を垂れ流し、著作権侵害の訴訟リスクを山ほど抱えていたYouTubeを、Googleは16.5億ドル(当時のレートで約2000億円)という巨額で買収しました。当時、多くのメディアや専門家は「狂っている」「高すぎる買い物だ」と酷評しました。[15]
しかし、結果はどうだったでしょう。GoogleはYouTubeの膨大なトラフィックを自社の広告システムと結びつけ、世界最大の動画プラットフォームへと育て上げました。今やYouTubeは、Googleの親会社であるAlphabetの収益の柱の一つであり、その企業価値は買収額の100倍以上とも言われています。もしGoogleがあの時「狂った」決断をしていなければ、今日のYouTubeは存在しなかったかもしれません。
日本の大企業がスタートアップを買収しても、PMIがうまくいかないケースが多い。PMIとはPost Merger Integrationの略で、買収後の統合プロセスのことです。だからM&Aが広がらず、IPO一択になってしまう。この悪循環を断ち切るために、経産省はM&Aを合理的な選択肢として公式に認めたわけです。
ポイント3: 成長ステージに応じたガバナンスの共創
増補版のもう一つの大きな特徴が、ガバナンスを投資契約と一体で考えるという発想です。ガバナンスとは、企業の経営を監督し、正しい方向に導くための仕組みのことです。
宮下弁護士は動画の中で、グレイナーの企業成長モデルを引用しています。経営学者ラリー・グレイナーが1972年に提唱した理論で、企業は成長の過程で5つの段階を経て、それぞれの段階で異なる危機に直面するというものです。[9]
たとえば、創業期は創業者のカリスマ性と創造力で成長するけれど、組織が大きくなるとリーダーシップの危機が訪れる。組織を体系化して乗り越えると、今度は自主性の危機が来る。こうした危機を乗り越えるたびに、経営のやり方を進化させていく必要がある。
増補版では、この考え方をスタートアップのガバナンスに適用しています。
| 成長ステージ | ガバナンスの特徴 | 求められる変化 |
|---|---|---|
| シード期 | 創業者が株主かつ経営者。大胆で迅速な意思決定 | 創業者のビジョンが最優先 |
| アーリー期 | VCからの資金調達。取締役会の設置 | 独立社外取締役の参画、監督機能の導入 |
| ミドルからレイター期 | 海外投資家の参入。大規模な資金調達 | 取締役会の構成強化、所有と経営の分離 |
| プレIPOから上場後 | 公開市場での説明責任 | モニタリング・ボードへの移行 |
ここで興味深いのが、日米の違いです。
日本では、IPO後も創業者がCEOを続けるケースが圧倒的に多い。創業時の株主が高い持株比率を維持し、取締役会も監督機能と執行機能を兼ねる傾向があります。
アメリカでは、成長段階に応じてCEOが交代することが珍しくありません。創業者が優れたビジョナリーであっても、組織が大きくなった段階では、大規模組織のマネジメントに長けたプロ経営者にバトンタッチする。取締役会には社外取締役や投資家取締役が多く参画し、経営を監督する機能が明確に分離されています。
増補版が提唱しているのは、ガバナンスを上場するための形式的な要件ではなく、企業価値を持続的に高めるための仕組みとして捉え直すこと。投資家と経営者が対話を通じて、その会社の成長ステージに最適なガバナンスを一緒に作っていくという考え方です。
ポイント4: 投資契約の英文化とグローバル標準への準拠
増補版では直接的に言及されていませんが、日本取締役協会は2023年の提言で、投資契約をグローバルスタンダードに準拠した英文で作成すべきだと主張しています。[4] 2023年7月には、モデル英文投資契約も公表されました。
地味に見えて、これは大きな変化です。契約書が英語で、しかもシリコンバレーのVCが見慣れた形式で作成されていれば、海外投資家は既存の投資契約のリスクを迅速かつ正確に評価できる。日本語の契約書を翻訳して、日本独自の条項を一つ一つ確認して…という膨大なコストがなくなるわけです。
宮下弁護士は、北欧のモデルを参考にしたグローカル成長投資モデルを提唱しています。[4] 創業期はローカルのVCが支援し、アーリー期以降はFounders Fund、Accel Partners、Andreessen Horowitz、Sequoiaといったグローバルトップのファンドに参加してもらう。彼らの巨大な資金力とグローバルなビジネスネットワークを借りて、日本発のスタートアップを世界に送り出す。
北欧は国内市場が小さいため、スタートアップは最初からグローバル市場を見据えて事業を設計します。国内VCとグローバルVCの明確な役割分担に基づく協業モデルが確立されている。日本もこれに倣おう、というわけです。
S&P495の衝撃: GAFAMなき米国経済は日本と同じ
ここで一つ、衝撃的な事実を紹介します。
米国の代表的な株価指数であるS&P500から、GAFAMの5銘柄を除いた「S&P495」のパフォーマンスは、日本のTOPIXとほぼ同じだそうです。[4]
つまり、アメリカ経済の圧倒的な強さの源泉は、GAFAMという数社の巨大テック企業にある。そしてこれらの企業は全て、もとはスタートアップでした。しかも、自社だけで成長したのではなく、有望なスタートアップを次々と買収することで、非連続的な成長を実現してきた。
逆に言えば、日本にGAFAMのような企業が1社でも2社でも生まれれば、日本経済の景色は一変する可能性がある。そのためには、スタートアップが大きく育つための資金とルールの整備が不可欠です。経産省の増補版は、まさにその土台を作ろうとしている。
私が考える、この変化の本当の意味
ここからは、株式会社TIMEWELL濱本としての個人的な見解を少し書かせてください。
正直なところ、今回の増補版だけで全てが変わるとは思っていません。ルールを変えても、それを使いこなす人材やマインドセットが追いつかなければ、絵に描いた餅で終わる。
でも、私がこの動きに強い希望を感じているのは、問題の構造がようやく正しく認識されたと思えるからです。
これまで日本のスタートアップ支援は、起業家を増やそう、補助金を出そう、インキュベーション施設を作ろう、といった裾野の拡大に重点が置かれてきました。それ自体は正しい。でも、いくら種を蒔いても、育つための土壌が整っていなければ、大きな木は育たない。投資のルールや市場の構造という土壌の問題に、今回初めて本格的にメスが入った。
しかも、株式買取請求権は設けるべきではないという、かなり踏み込んだ表現で。これは経産省の中にも、このままではまずいという強い危機感があったことの表れだと思います。
余談ですが、私がスタートアップの世界に身を置いていて感じるのは、日本の起業家の技術力やアイデアは、世界と比べても全く引けを取らないということ。むしろ、ものづくりの精緻さや、顧客の課題を深く理解する力は、日本の起業家の大きな強みです。
足りなかったのは、その強みを世界規模で花開かせるための仕組み。今回の増補版は、その仕組みの根幹を変えようとしている。だからこそ、私はこの動きに注目しているし、一人でも多くの人に知ってほしいと思って、この記事を書いています。
このルール変更で、日本の未来はどう変わるのか
この変化が順調に進んだ場合、日本のスタートアップ・エコシステムはどう変わっていくのか。私なりに考えてみます。
海外マネーの流入による成長資金の充実
ガラパゴス条項が撤廃され、投資契約がグローバルスタンダードに準拠すれば、海外の大型VCファンドが日本市場に参入しやすくなります。Sequoia Capital、Andreessen Horowitz、Tiger Globalといった、1件あたり数十億円から数百億円を投じるファンドが日本のスタートアップに投資するようになれば、レイター期の資金不足という構造的な課題が解消に向かうでしょう。
ディープテック分野での飛躍
十分な成長資金が得られれば、日本のスタートアップはAI、量子コンピューティング、創薬、宇宙、GXといった、大規模な研究開発投資が必要なディープテック分野で、世界と勝負できるようになります。GXとはグリーン・トランスフォーメーションの略で、脱炭素社会に向けた産業構造の転換を指します。
Preferred NetworksやSakana AIのように、世界レベルの技術力を持つ日本のスタートアップは既に存在しています。彼らに十分な資金が供給されれば、日本発のグローバル・テックカンパニーが生まれる可能性は十分にある。
M&Aの活性化による産業の新陳代謝
M&Aが合理的な選択肢として定着すれば、日本の大企業とスタートアップの関係も変わります。大企業がスタートアップを買収し、自社のリソースを活用してスケールさせる。スタートアップ側も、IPOだけに縛られず、最も成長を加速できるパートナーを選べるようになる。
これは日本経済全体の新陳代謝を促進する効果もあります。既存の大企業が新しい技術や事業モデルを取り込み、自らも変革していく。そうした好循環が生まれれば、失われた30年からの脱却も夢ではないかもしれません。
そして、その兆しは既に見え始めています。2021年、米決済大手のPayPalが、日本の後払い(BNPL)サービス大手であるPaidyを3000億円で買収しました。これは、日本のスタートアップのM&Aとしては過去最大級の案件であり、海外の巨大テック企業が日本のフィンテック市場の将来性高く評価した証左と言えます。Paidyの成功は、日本のスタートアップもグローバルレベルで評価され、大型M&Aの対象となり得ることを証明しました。
起業家にとってのセーフティネットの充実
株式買取請求権や連帯保証が撤廃されれば、起業に失敗した際のリスクが大幅に軽減されます。失敗したら人生が終わるという恐怖がなくなれば、優秀な人材がもっと起業に挑戦するようになるでしょう。
シリコンバレーでは、失敗は名誉の勲章とさえ言われます。一度失敗した起業家が、その経験を活かして次のベンチャーで大成功する、というストーリーは珍しくない。日本でもそうした文化が根付けば、スタートアップ・エコシステムの厚みは格段に増すはずです。
まとめ: 契約書の向こうに見える、この国の未来
長い記事にお付き合いいただき、ありがとうございます。
今回お伝えしたかったのは、経産省の新ルール増補版が、単なる契約書のテクニカルな話ではないということ。日本のスタートアップ・エコシステムの鎖国を終わらせ、世界中の才能と資金を呼び込むための、国を挙げた大きな方向転換の一環です。
もう一度、要点を整理します。
| 課題 | 増補版の対応 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 株式買取請求権 | 設けるべきではないと明記 | 海外投資家の参入障壁撤廃 |
| IPO偏重の出口構造 | M&Aやセカンダリーを合理的選択肢と明記 | 出口手段の多様化、成長戦略の柔軟化 |
| 画一的なガバナンス | 成長ステージに応じた動的なガバナンス設計を推奨 | 企業価値の持続的向上 |
| 国内閉鎖的な投資慣行 | グローバルスタンダードへの準拠を推進 | 海外資金の流入、エコシステムの国際化 |
ルールが変わっただけで、明日すぐに日本からGAFAMが生まれるわけではありません。でも、土壌が変われば、そこから育つ木の大きさも変わる。
宮下弁護士の動画を見て、私が一番印象に残ったのは、エコシステム全体の最適化という言葉でした。投資家と起業家がそれぞれの利益を最大化するのではなく、エコシステム全体として最適な仕組みを作る。その発想の転換こそが、日本のスタートアップが世界で戦うための出発点なのだと思います。
この記事を読んでくださった皆さんが、投資契約という一見とっつきにくいテーマの向こうに、日本の未来を変える大きな可能性を感じてくれたなら、書いた甲斐があります。
あなたの持ち場で、何ができるか
最後に、この大きな変化の波の中で、私たち一人ひとりが何ができるのかを考えてみたいと思います。
もし、あなたがスタートアップの起業家、あるいはこれから起業を考えている方なら。
今回の増補版は、あなたにとって強力な追い風です。海外の投資家と対等に渡り合えるルールが整備され、M&Aという現実的な選択肢も手に入った。もはや「小さな上場」をゴールにする必要はありません。最初から世界市場を見据え、大きなビジョンを描いてください。そして、投資家を選ぶ際には、単なる資金の出し手としてではなく、あなたのビジョンを共有し、共に成長を目指せるパートナーを選んでほしいと思います。
もし、あなたが大企業に勤めている方なら。
あなたの会社も、この変化と無関係ではありません。自前主義の限界が明らかになる中で、スタートアップとの連携、そしてM&Aは、企業が生き残るための重要な戦略になります。社内にスタートアップの技術や文化を取り入れる「オープンイノベーション」の担当者として、あるいは新規事業の責任者として、ぜひアンテナを高く張ってください。あなたの会社のリソースと、スタートアップの機動力が組み合わされば、想像もつかない化学反応が起きるかもしれません。
もし、あなたが投資家、あるいはこれからエンジェル投資を始めたいと考えている方なら。
日本のスタートアップ市場は、今がまさに黎明期です。グローバルスタンダードなルールが浸透していく過程では、一時的な混乱もあるかもしれません。しかし、長期的に見れば、大きな成長のポテンシャルを秘めています。S&P495の衝撃を思い出してください。GAFAMが生まれる前の米国経済と、今の日本は似ています。次のGAFAMが日本から生まれると信じて、リスクを取り、未来に投資する。そんな気概のある投資家が一人でも増えることを願っています。
そして、もしあなたが、特定の立場にはない一人のビジネスパーソンだとしても。
この国の未来を形作るのは、政治家や一部のエリートだけではありません。私たちが日々、どんな情報に触れ、何を考え、どう行動するかの積み重ねが、社会の空気を作ります。「どうせ日本は変わらない」と諦めるのではなく、「こうすればもっと良くなるんじゃないか」と前向きな議論を始める。この記事が、そのための小さなきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。
一緒に、この国の未来を、もっと面白くしていきましょう。
株式会社TIMEWELL 濱本
参考文献
[1] 内閣官房. (2022, November). スタートアップ育成5か年計画. https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/
[2] 経済産業省 イノベーション・環境局. (2025, December 2). スタートアップ・エコシステムの現状と経済産業省の取り組みについて. https://www.fsa.go.jp/policy/pjlamc/roundtable/01.pdf
[3] 経済産業省 総合科学技術・イノベーション会議 イノベーション・エコシステム専門調査会 資料.
[4] 宮下和昌. (2023, September 12). 我が国のベンチャー・エコシステムの高度化に向けた提言. 日本取締役協会. https://www.jacd.jp/news/column/column-opinion/230912_post-295.html
[5] Blackbox. (2025, December 26). New rules for "Foreign Funding for Startups" revise Japan's unique practices. https://www.blackboxjp.com/news/new-rules-for-foreign-funding-for-startups-revise-japans-unique-practices
[6] 日本経済新聞. (2025, May 27). 機関投資家がいないのに グロース企業、上場維持基準上げに戸惑い.
[7] 東京証券取引所. (2025). グロース市場における今後の対応. https://www.jpx.co.jp/equities/follow-up/
[8] 経済産業省. (2025, September). 我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項 増補版. https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startup_investment_agreement_guidelines/startup_investment_agreement_guidelines.html
[9] Foundor.ai. (2025, January 17). グライナー成長モデル: ビジネス成長の5つのフェーズ. https://foundor.ai/ja/blog/greiner-growth-model-guide
[10] 経団連 21世紀政策研究所. (2001, December). 日本のベンチャー・キャピタルの歴史と現状. https://www.keidanren.or.jp/pri/storage/pdf/thesis/011212_21.pdf
[11] Wikipedia. Yozma. https://en.wikipedia.org/wiki/Yozma
[12] 東洋経済オンライン. (2020, March 27). 「失われた30年」の本質. https://toyokeizai.net/articles/-/325346
[13] JETRO. (2024, March 1). シンガポールのスタートアップ支援策. https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2024/0301/106a86a4daf713ba.html
[14] AZX弁護士法人. (2022, January 13). みなし清算条項とは. https://www.azx.co.jp/knowledge/2807
[15] Medium. (2024, May 5). Google's Successful Acquisition of YouTube. https://medium.com/@davidsehyeonbaek/googles-successful-acquisition-of-youtube-797bc6e2461d
[16] IMD. (2025). World Competitiveness Ranking. https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking/